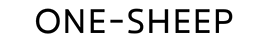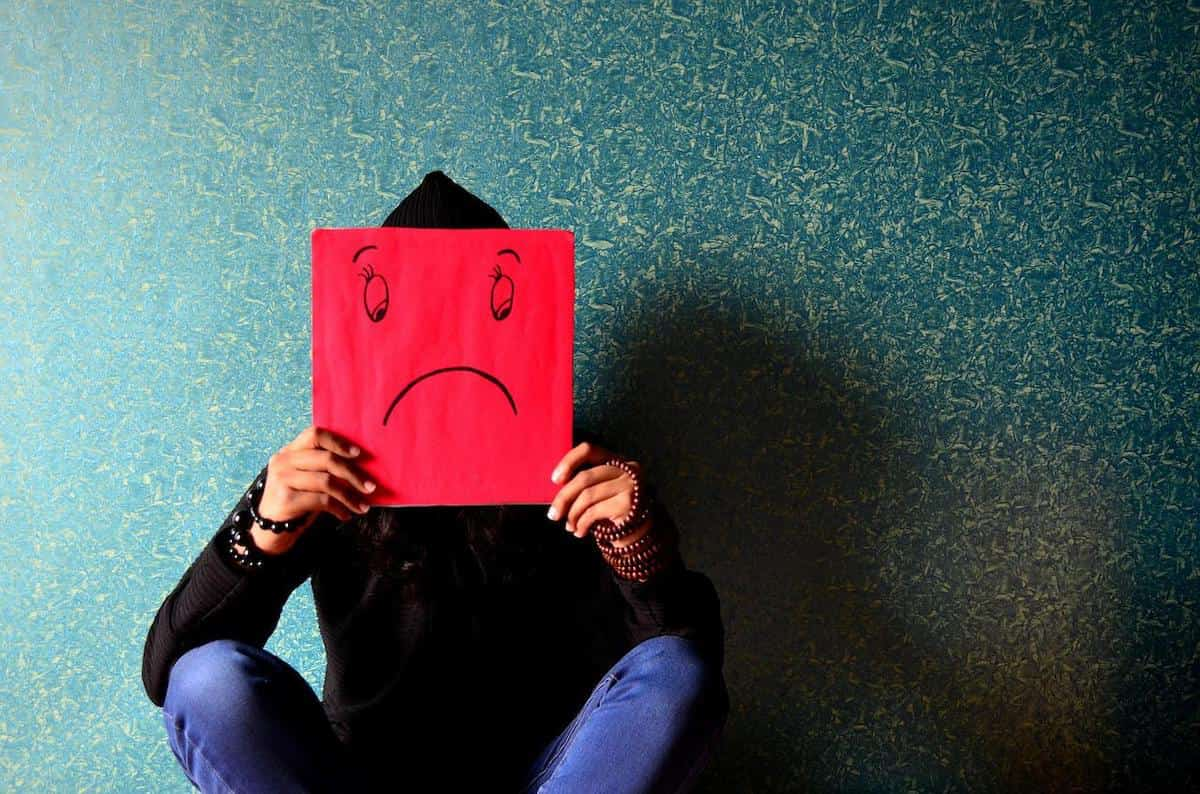何がしたいかわからない。進路を選ばぬ先は?【ちきりんさんに学ぶ】
こんにちは、うなんです。
「何がしたいかわからない」学生時代を送りました。

学生「将来、何がしたいかわからない。どんな仕事が向いてるかも、わからない。進路、どうしよう…」
↑このような学生は、あなただけじゃないです。
ちなみにわたしの経歴は、
- 大学付属の高校に入り→大学受験せずエスカレーター式に進学
- 将来やりたいこともないし、サークル活動とかしてなんとなく過ごす
- 就活が始まるその瞬間まで、将来の職業イメージをまったく意識せず
こんな感じ。
いかにも能天気な若者…ですが、正直、こういう人も少なくはないでしょう。
就活するまで仕事について考えてこなかったのだから、もちろん、いきなり自分に合った進路を選べるわけもなく…。
「何がしたいかわからない」のは、何も考えてこなかった自分自身の責任ですが、
「何も考えてない若者でも、己の能天気さに気が付かずに大学卒業・就活まで進める」
こんな教育の構造も、問題の根底にはあると思います。
今回は、『Chikirinの日記』を読みながら、わたしがうなずいたことをピックアップして、「人生を選ぶ機会」について考えます。
目次
↑「教育論や体験談はどうでもいいから、進路の見つけ方を知りたい」という切羽詰まった学生は、目次の3つ目まで飛んでもOKです。
何がしたいかわからない。進路を考える機会について

ここからは、ちきりんさんの記事『いい人生の探し方』を引用しつつ、進めます。
人生について考える&選ぶ機会の少なさ
『いい人生の探し方』は、中学から大学までエスカレーター式に進める学校に通っていたMさんが、進路選びで「(端的に言うと)失敗」してしまったという話がテーマです。
「やりたいことがわからない、将来を適切に選べない」のは、10代での「人生を選ぶ練習」の機会がなかったためであり、その結果、Mさんはまちがった道を選んでしまいました。
大学受験をする高校生は、17歳の段階で、「どこの大学にいこうか」&「どこの学部を受けようか」と考え、親や友達とも意見を交わします。
この時、大学名や学部だけでなく将来のキャリアについても併せて考えます。
ところが受験なしに大学に行ける場合、この10代での「考え&選ぶタイミング」が飛んでしまいます。
大学受験をする子が17歳で最初に「自分の将来像」と向き合うのと比べ、そのタイミングは5年近くも遅れてしまうのです。
(一部中略)
「超明確にやりたいことがある子」ならいいのですが、そういう子はそれほど多くはないでしょう。
内部進学できることによる、「人生を考える機会の損失」が生まれてしまっています。
そして、もっと重要だと思うのが、次です。
問題は「職業イメージを選ぶタイミングの遅れ」だけではありません。
大学受験を経験した子は、大学での就活時が2回目の「将来像の検討タイミング」になるので、最初の思考の間違いが修正できます。
17歳で一度は考えて選んだ職業イメージにたいして、大学時代に振り返ることができ、それを就活の時に修正して2回目の選択ができるわけです。
一方、「エスカレーターに乗って大学に入りました。学部も高校の成績で決めちゃいました」みたいな内部進学生は、大学で就活が始まってから初めて「さて、何になりたいんだっけ?」と考え始めます。
(一部中略)
初めて考えたアイデアが、うまくいくなんてことは、そうそうありません。
それなのに、多くの内部進学生は、就活のときに「自分の将来を考える初めてのタイミング」を迎えます。
「将来の仕事を見すえて選んだけど、やってみたら、なんか違ったな」という経験が、あるのとないのとでは大違いです。
「ふりかえりと修正」の経験がないまま就活に突入すると、社会人になってから「なんかちがった」という失敗にぶち当たる可能性が、とても高い。
できるだけ早いうちに、「選ぶ→やってみる→修正する」を体験したほうがいい、ということですね。
将来を考える練習はもっと早くからやるべき
「人生を選ぶ」ことについては、学校教育をテーマに、ちきりんさんとプロゲーマーの梅原大吾さんが対談されたこの本↓も、めちゃくちゃ面白いです。
日本の学校教育では、「いい人生へのゴールはここで、そのための道筋はこう」って、大人からある種の「正解」を刷り込まれます。
「いい学校を出て、大きな会社に就職するのがいい人生」で、そのためには「勉強してテストでいい点数を取りなさい」と。
素直にその「学校的価値観」にしたがう子どもたちは、自分の頭で考えたり、もがく体験をしません。
テストの点が取れれば、成績がよければ、成功なんです。
だから、「やりたいこと」もずっとわからないまま、学校で正解だと教えられたほうに、大人になってもなんとなく乗っかってしまう。
ほんとうは、もっと若いうちから、自分の将来を考える練習をしないと、やりたいことって見つからないんですよね。
学校の中で思考停止させられていたら、自分がほんとうは何がしたいかなんて、わかるようにならない。
「大人になったら何になりたいの?」とたまに大人から聞かれるくらいでは、将来を考えるには足りません。
- 将来の自分の職業イメージを持つ
- それに向けてやるべきことを自分で選んでやる
- やってみて違うと思ったら、別のものを選んでやる
このプロセスのくり返しで、ようやく、自分なりの正解に近づいていけるんだと思います。
私自身は17歳で最初の選択をし、22歳でその選択を変更し、さらに30歳で別の選択をして、そのあと35歳でようやく「コレだ!」を見つけました。
なんとそこまで4回の試行錯誤が必要だったんです。
考えただけでは、ほんとうに自分に合っているのか、わからないですし、ましてや最初から正解を引くことは、ほとんどの場合できません。
私は、就活で初めて職業について考えて、「とりあえずコレかな」と最初の会社を選んで、やっぱり違くて、新たな選択をしました。
やり直せる間に、何度も「人生を選ぶ練習」をできるように、早いうちから考え始めたほうがいいですね。
「やり通すが正義、やめるは失敗」の思考のわな
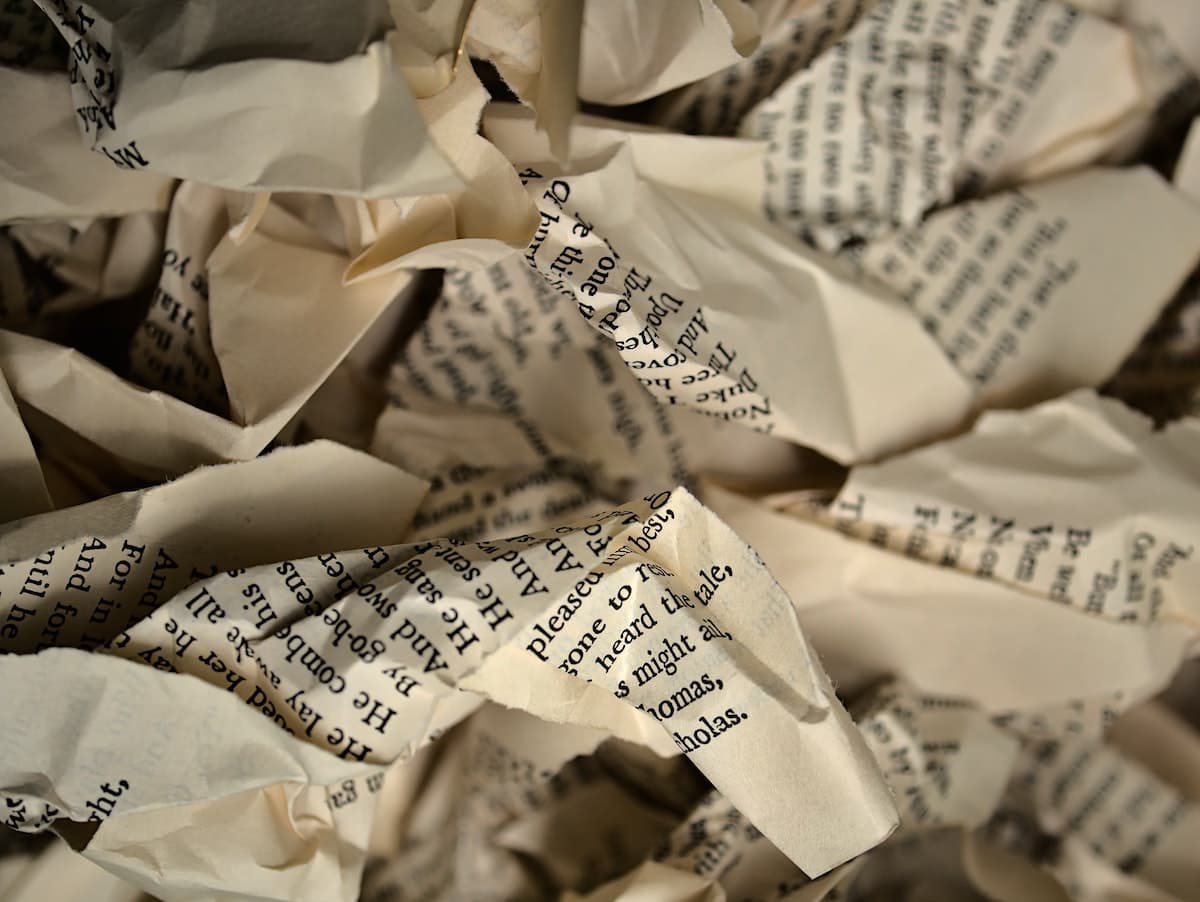
日本人の風習、感覚として、「一度始めたことはやり続けるべき」という思考が根深くあります。
いわゆる、「石の上にも三年」の考え方です。
- 一度務めた会社は、少なくとも3年は続けないとダメだ
- 努力し続ければ、いつか事態が好転して、きっとうまくいく
しかし、現代の生き方には、そぐわないですよね。
ストレスがあってもお金が全然稼げなくても、細々と生きていければいいのなら、それでもなんとかなるかもですが…
「とにかく続けさえすればいい」という考えは、ひたすら弱者になる思考です。
1つのことだけに固執する必要はない
仕事に関しては、エミリー・ワプニックの『マルチ・ポテンシャライト』という考え方がユニークなので、ここで紹介しておきます。
「何か1つのプロフェッショナルになって、生涯続ける」のが向かない人なら、こういう考え方もアリですね。
むしろ、こういう人のほうが力を手に入れていくと思います。
くわしく知りたい方は、エミリーの著書を読んでみてください。
学校的価値観にしばられている人にとって、ブレイクスルーになるかもしれません。
損切りと変化の早さで勝つ
日本人は特に「一度はじめたことを、やめるのは恥」と思っています。
しかし、「逃げるは恥」の意識でいると、たとえ明らかにまちがった方向へ進んでいるときも、いつまでもやめる踏ん切りがつきません。
「たくさんのお金や時間を費やしたのだから、成功するまで続けなきゃ」 と、諦められないのは、墓穴をほっているだけです。
損切りのタイミングが遅いと、失敗や大きな損を引き寄せ続けます。
(ちきりんさんの過去の記事『Exit』でも、「撤退ができない日本人」について書かれています。)
ビジネスの世界なら、柔軟に変化し続けられる人が勝ちます。
これは、個人単位の人生でも同じことです。
今、高校生や大学生の子たちが、進路を見つけるためにできること
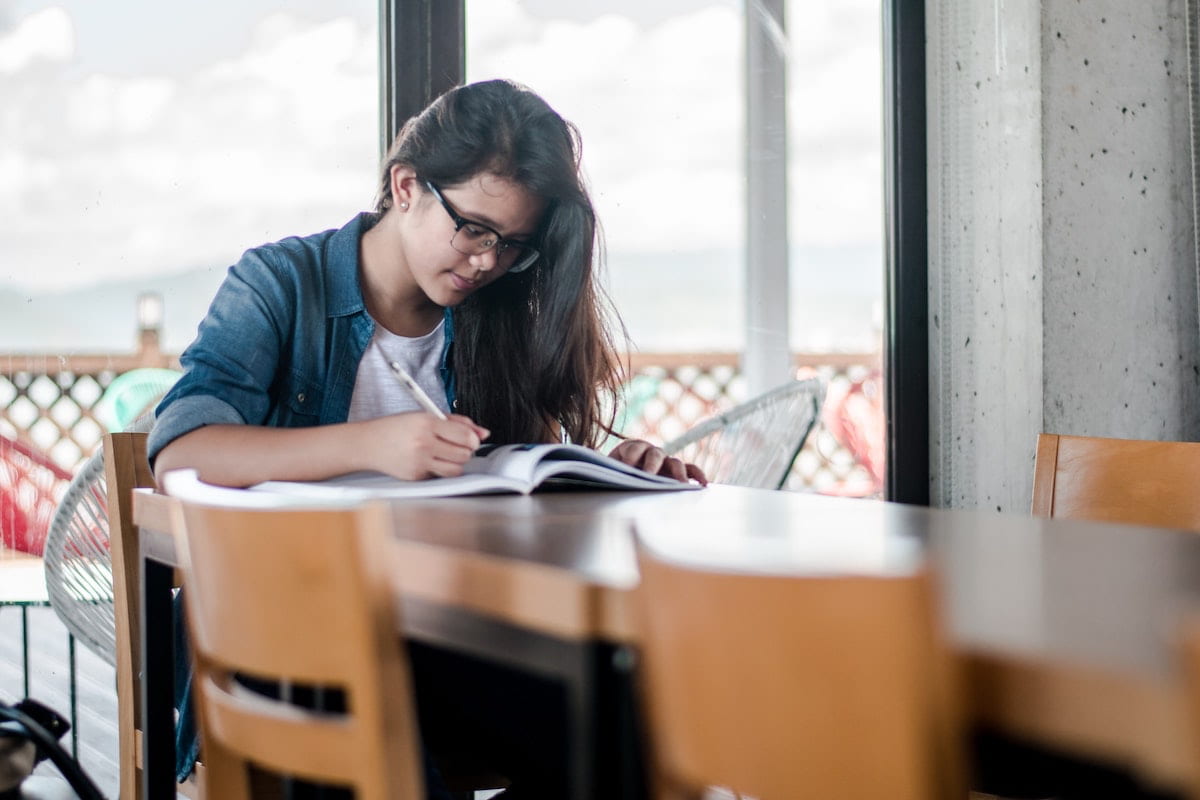
さて、「今まさに、人生を選ばなくては」というタイミングにある学生は、どうしたらいいだろう、ということを最後に書きます。
「こっちの道が平坦でいいよ、あなたにぴったりだよ」なんて道しるべを、他人は用意できませんから、最終的には自分で考えて、やってみるしかありません。
自分で考えて、動きましょう!
いま、高校生なら
「現時点での自分の将来像と職業イメージ」を考えて、それに向かう道を選びましょう。
大学進学でも、専門学校でも、次のフェーズでまた、進路を選ぶタイミングがきます。
そのとき、「やっぱり違ったな」と思ったら、あらためて目標を修正すればOKです。
失敗するほど、「コレだ」というものに近づけるはず。
機会も時間もあるので、やりたいと感じたことから順番に、試していってください。
いま、「就活はもうちょっと先だけど…」という大学生なら
将来の職業イメージを抱きつつ、興味のあることを片っ端からやってみましょう。
「やってみる」→「なんか違う」→「じゃあ別のやってみる」
このサイクルを回さないと、やりたいことやできることは見つかりません。
とりあえず、試しましょう。
ここで注意すべきなのは、「一斉にいろいろと手をつけない」こと。
1つのことをとことんやって、ダメなら次、と順番にやります。
くわしくはこちらの記事を参考にしてください。
» 参考:やりたいことがない理由&3ステップでやりたいことを見つける方法
いま、まさに就活中or間近なら
「周りの子たちは、なんかやりたいこと、ちゃんとあるっぽい…」
と焦ったりせず、自分の将来像と向き合いましょう。
いろいろと試さないと、ほんとうに何がしたいかはわからないですが…
片っ端から試す時間がないのであれば、現時点で一番興味のありそうな分野を調べるべし。
ちなみに内定出たり、就職したあとも、ほんの少しでも気になる分野の勉強は、つねに自主的にやっておくと良いです。
就職してから「この仕事、やっぱり違ったな」という可能性はあるので、そんなときすでに勉強をしていれば、現職と異なる分野でもすぐにチャレンジしやすくなります。
やりたいことを見つけるために
最後にふりかえっておくと、大事なのは以下のサイクルです。
- 将来の自分の職業イメージを持つ
- それに向けてやるべきことを自分で選んでやる
- やってみて違うと思ったら、別のものを選んでやる
この実験をくり返していくほど、失敗=実験結果が得られて、正解に近づいていきます。
とにかく「考える→実行する→修正する→実行する」ですね。
学生でこれに気づけたなら、手遅れということはないので、今日から動き出してみてください。
何年かかるかはわかりませんが、自分が何がしたいのか、見つけられるはずです。
今回は以上です。
それでは!